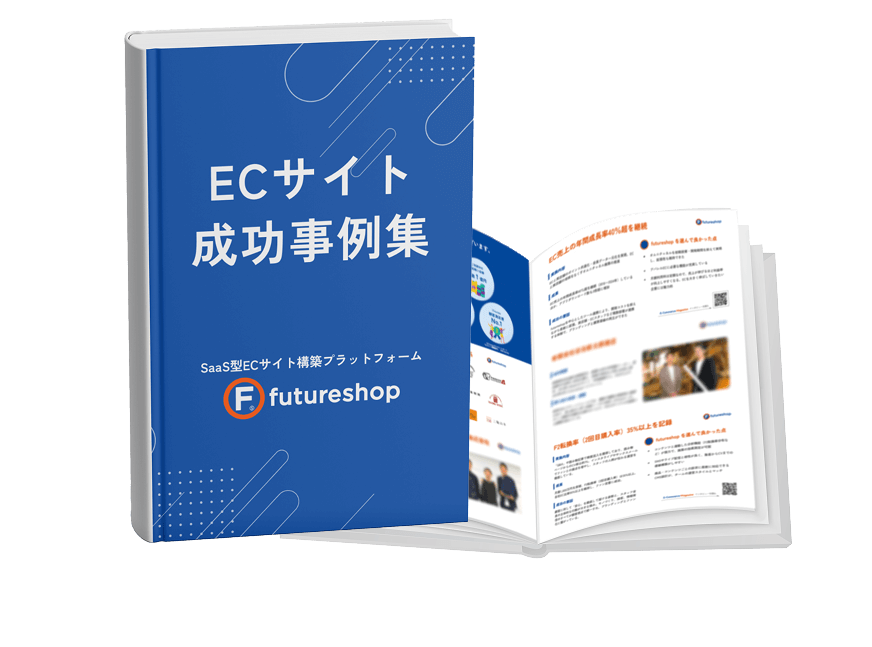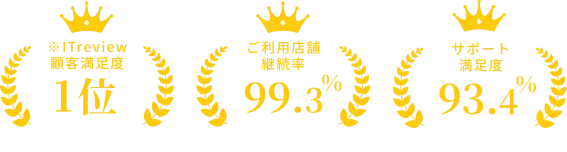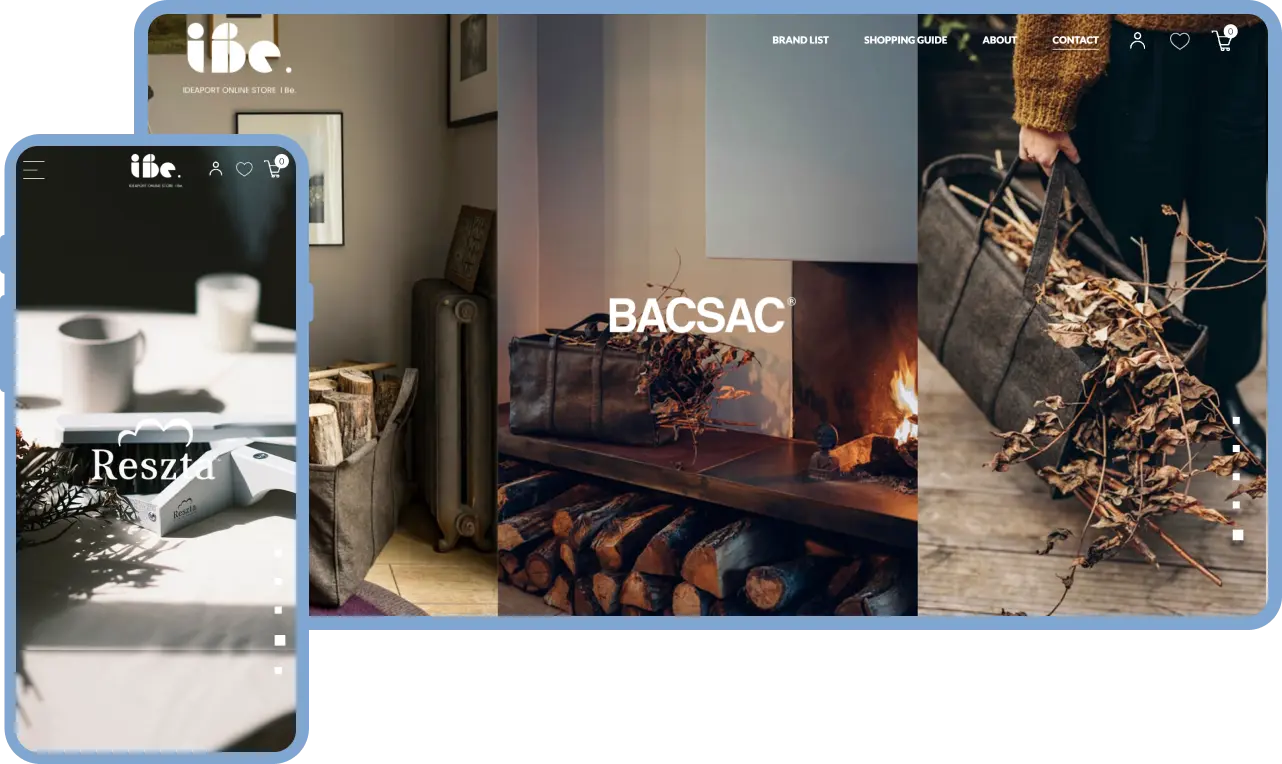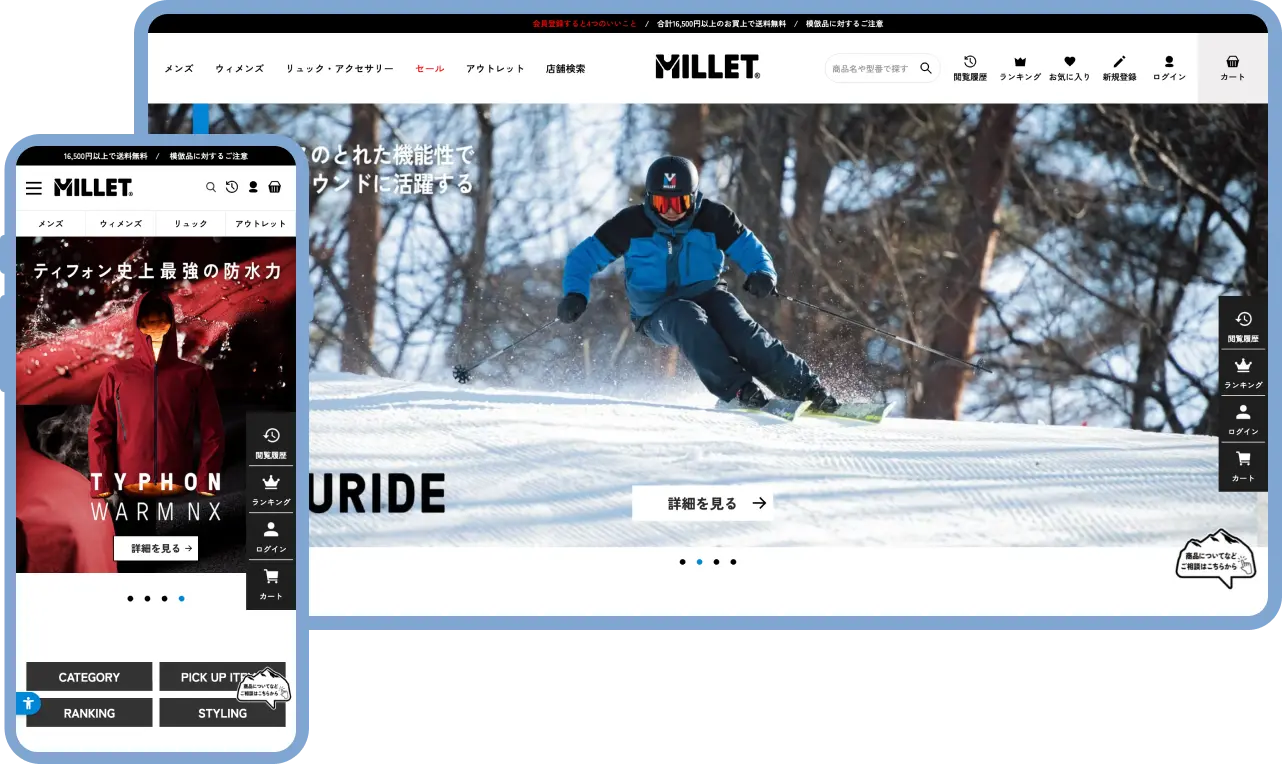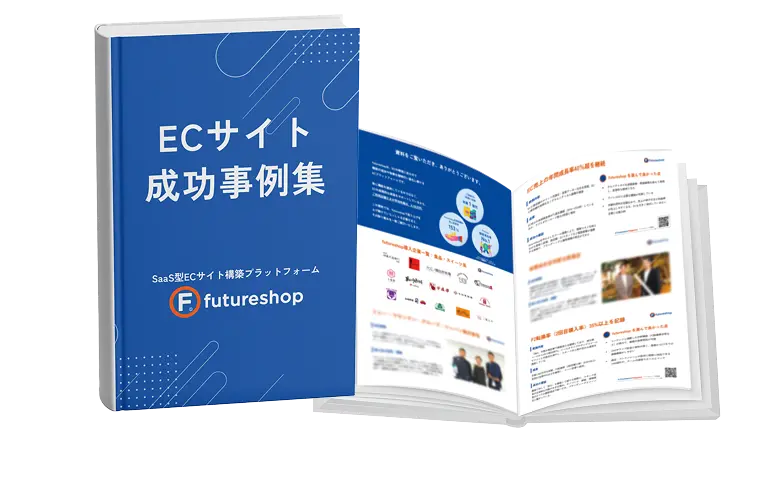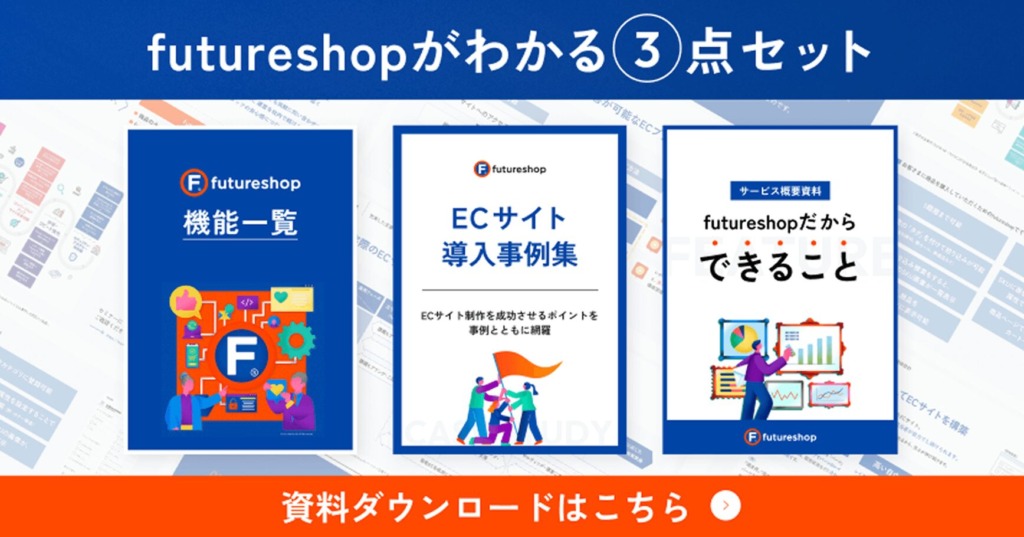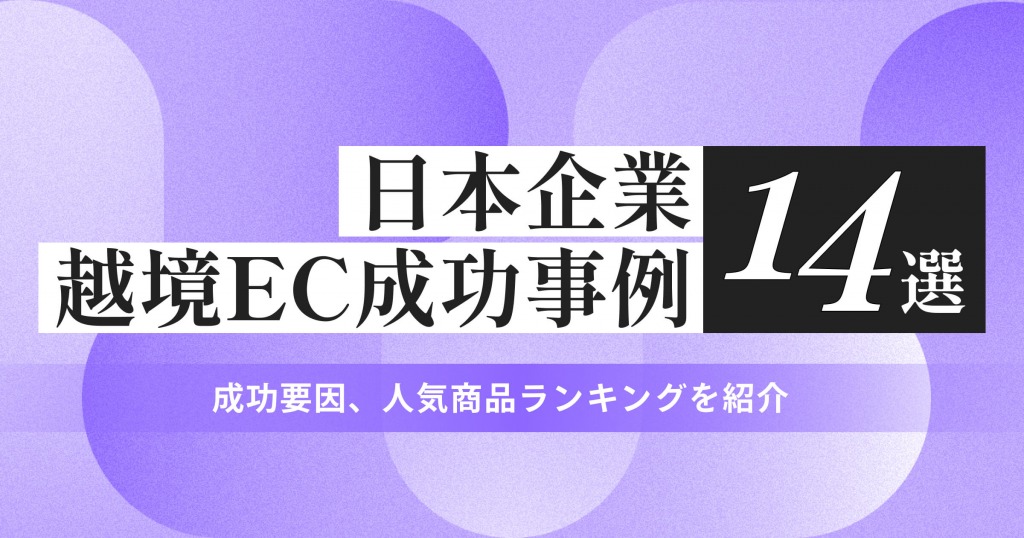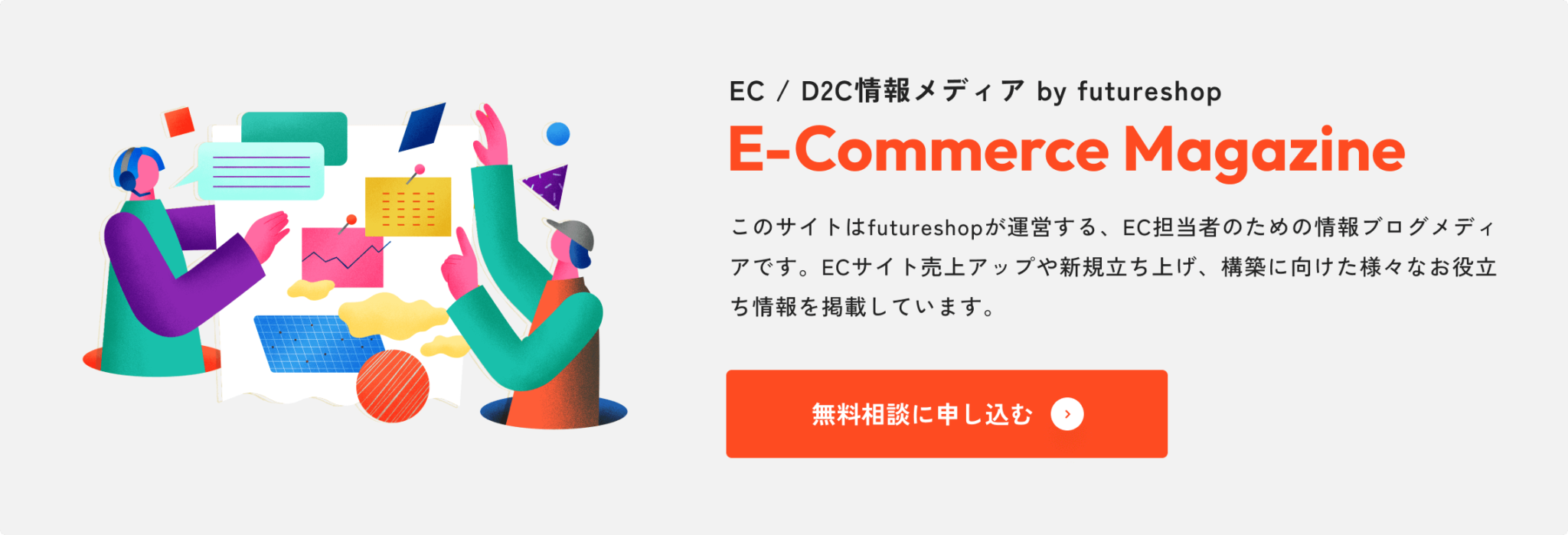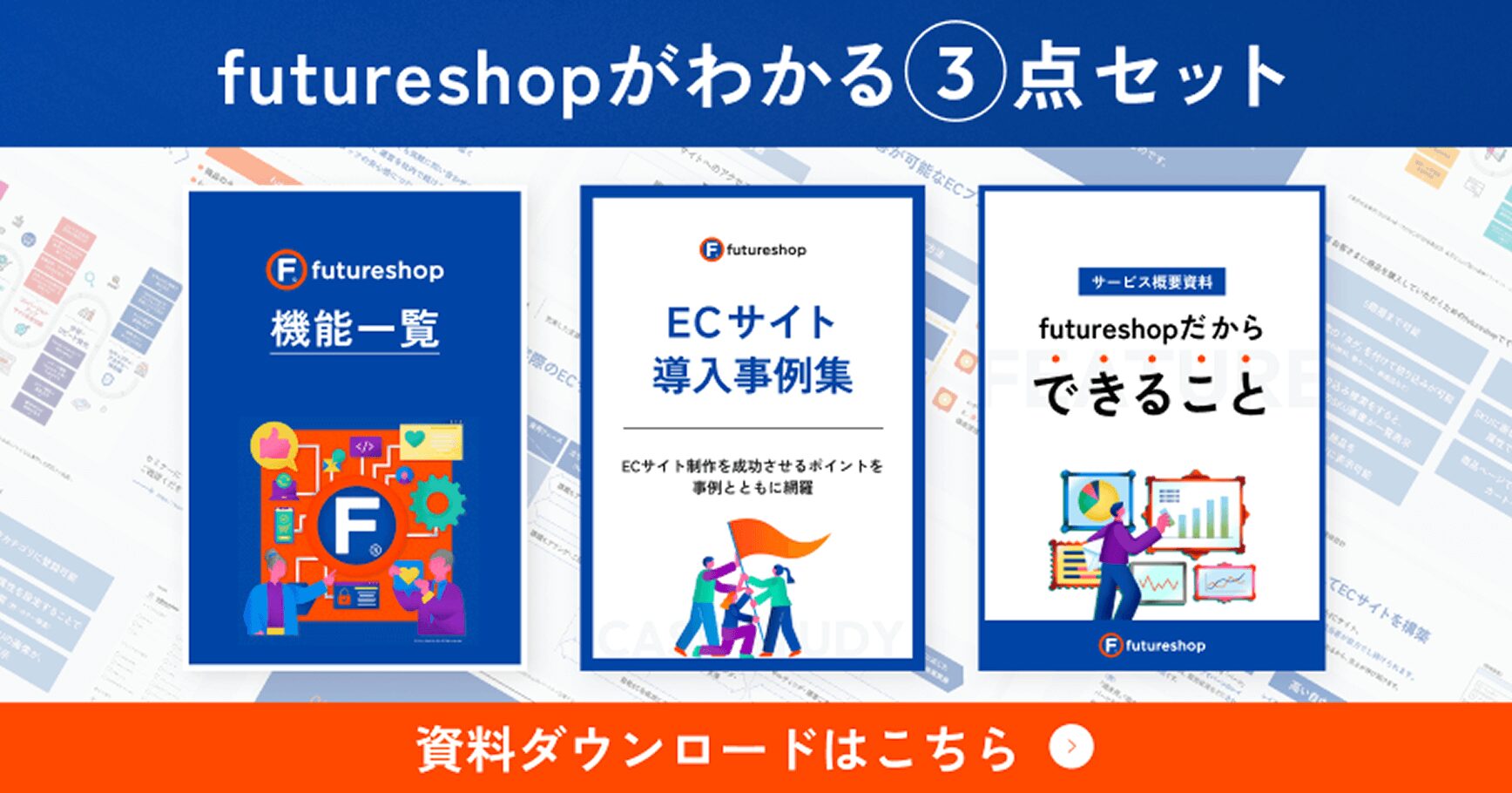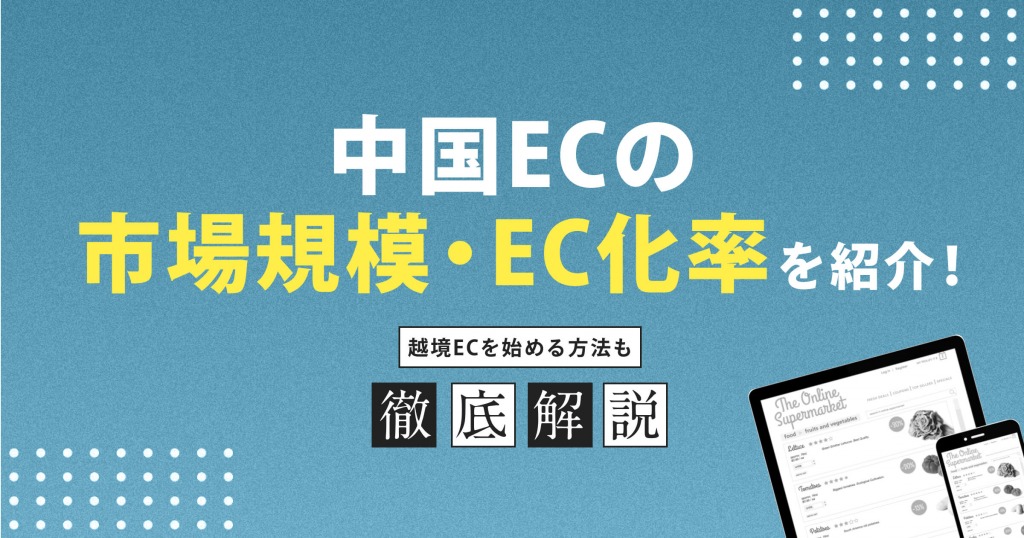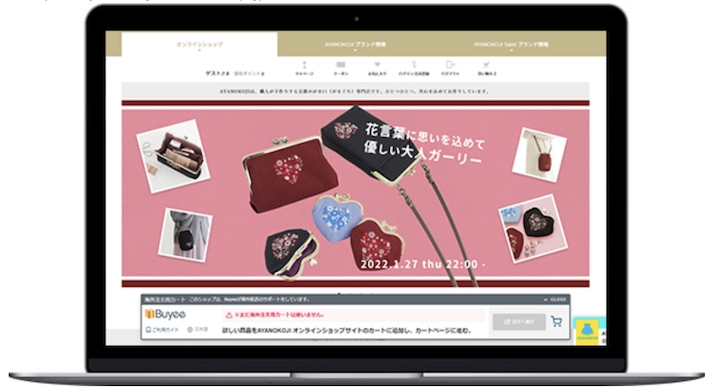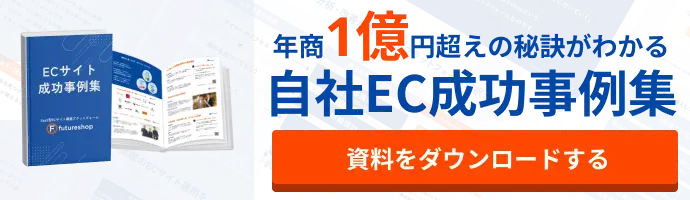食品越境ECの始め方|向いている食品や注意点も紹介
- 2025.07.25
2025.07.25
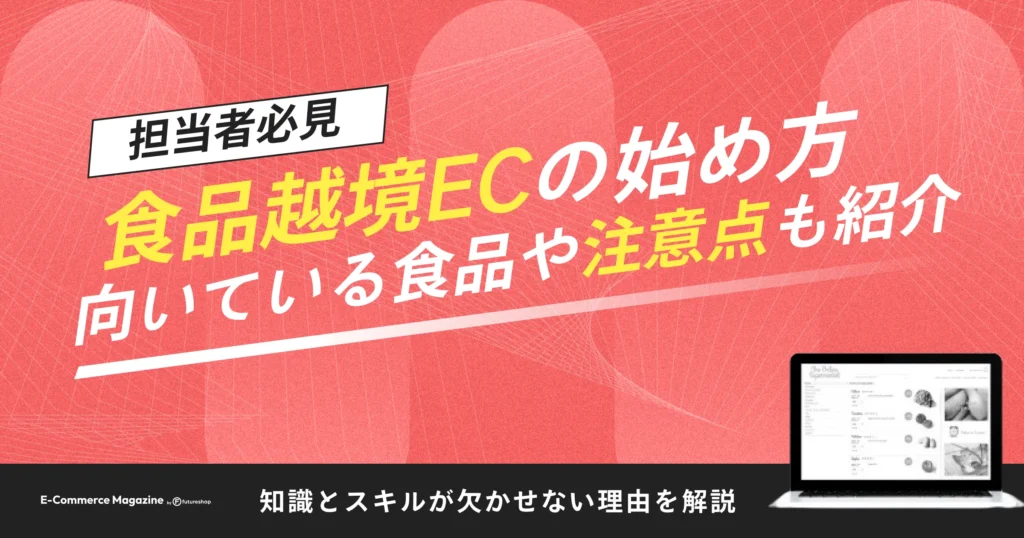
「食品越境ECを始めたい」「越境ECで食品を販売する際の注意点はある?」
上記のように、越境ECで食品を販売したいと考えている方もいるでしょう。日本の食品は、海外から高い評価を得ており、輸出額も年々増加傾向にあります(※農林水産省調べ)。越境ECを通じて海外に販売することで、事業拡大を期待できます。
また、中国向けの越境ECにおいて、商品開発から中国におけるデジタルマーケティング・翻訳・プロモーションなどの各種サポートを手がけた結果、1年間で中国事業の売上高が10倍になった食品メーカーも存在しており、越境ECは注目されているのです。(参照:【今すぐできる】越境ECの始め方|日本語サイトで海外に売る方法)
本記事では、食品越境ECの始め方を紹介します。食品越境ECを始める際の注意点や、おすすめな食品も解説しているので、食品越境ECに興味がある方はぜひ最後までご覧ください。
目次
越境ECで食品を販売するメリット
日本の食品は、品質の高さや安全性から海外での評価が高く、越境ECを通じて新たな市場を開拓する大きな可能性を持っています。国内市場が縮小傾向にあるなか、海外に目を向けることは事業成長にもつながるでしょう。
ここでは、食品を越境ECで販売することの具体的なメリットについて詳しく解説します。
実店舗運営よりもハードルが低い
越境ECで食品を販売するメリットは、実店舗運営よりもハードルが低い点が挙げられます。海外で実店舗を立ち上げるのは、現地の土地探しや店舗建設費、複雑な法規制への対応など、莫大な初期投資と時間やリスクが必要なため、高いハードルがあります。
しかし、越境ECであれば、リスクやコスト負担を大幅に抑えて海外市場に参入できます。既存のECサイトを多言語化したり、越境ECプラットフォームを活用したりすることで、物理的な店舗を持たずに、日本の食品を世界中の顧客に届けられます。事業開始までの期間も短縮され、よりスピーディーな海外展開が実現できるのが、越境ECのメリットです。
日本商品の品質の高さが強みになる
日本の食品は、海外市場において「安全」「高品質」「美味しい」などポジティブなイメージで強く認識されています。徹底した品質管理基準や素材へのこだわりは、世界中の消費者から高い評価を得ており「日本ブランド」としての信頼性は、越境ECで食品を販売するうえで強力な強みとなるのです。
また、海外の消費者は、日本の食品に対してある程度のプレミアム価格を支払うことに抵抗が少ない傾向があります。そのため、日本の食品事業者は、品質を前面に押し出して販売戦略を立てることが可能です。
事業拡大を期待できる
国内市場が縮小するなか、越境ECを通じて海外市場に参入することは、企業の事業拡大を期待できます。特に、経済成長が著しい中国やASEAN諸国をターゲットにすることで、従来の国内市場では獲得できなかった大規模な新規顧客層にアプローチが可能です。
ASEAN諸国などでは、日本食文化への関心も高まっており、日本の食品に対する需要が拡大しています。越境ECは、地理的な制約を越えて、手が届かなかった巨大な市場へ直接商品を届けられるため、売上やブランド認知度の向上を期待できるでしょう。
越境ECに向いている食品の特徴
日本の食品を海外に販売する越境ECは魅力的な選択肢ですが、すべての食品が等しく越境ECに適しているわけではありません。輸送コストや品質保持、現地の規制などを考慮し、越境ECと相性の良い商品を選ぶ必要があります。
ここでは、越境ECに向いている食品の主な特徴を6つ紹介します。
特徴1:常温で配送できる
越境ECで食品を販売する際、大きなハードルの1つが温度管理です。冷蔵や冷凍が必要な食品は、海外への長距離輸送中に品質を保つのが難しく、冷蔵設備や輸送ルートが求められるため、コストが大幅に上昇します。
そのため、常温で保存・配送が可能な食品が越境ECに適しています。具体的には、以下のような食品が挙げられます。
- レトルト食品
- 乾物(乾麺、乾燥野菜、海苔など)
- 日持ちのするお菓子
- 醤油や味噌などの調味料
温度変化による品質劣化のリスクが低く、通常の国際輸送で対応しやすいため、初期段階での越境ECにおすすめです。
特徴2:賞味期限が長い
海外への配送は、通関手続きや輸送経路、現地の配送状況によって想定以上に日数がかかります。賞味期限が短い食品では、消費者の手元に届く頃には期限切れが近づいてしまったり、過ぎてしまったりするリスクが高まります。
越境ECで取り扱う食品は、賞味期限が長いものを選ばなくてはなりません。具体的には、目安として6か月以上の賞味期限がある以下のような商品がおすすめです。
- レトルト食品
- 乾物
- 缶詰
- 個包装されたお菓子
- ボトル入りの調味料
賞味期限が長い食品を選ぶことで、顧客への品質保証と、廃棄ロスの削減にもつながります。
特徴3:軽量で体積が小さい
国際輸送における送料は、商品の重量や体積に応じて大きく変動します。特に航空便を利用する場合、重量だけでなく容積重量も考慮されるため、かさばる商品は送料が高くなる傾向があります。
そのため、越境ECで利益を確保するためには、軽量で体積が小さい以下のような食品を選ぶのがおすすめです。
- スナック菓子
- 個包装のサプリメント
- ティーバッグ式の緑茶
- フリーズドライ食品
上記のような商品は、一度に多くの量を輸送しても送料を抑えやすいため、コストパフォーマンスが高く、消費者にとっても購入しやすい価格設定が可能です。
特徴4:日本の歴史のある食品
海外では、食品としての味だけでなく、背景にある文化や歴史にも価値を見出す消費者が多く存在します。特に「日本の製品は品質が高い」という評価は世界共通であり、伝統的な製法や歴史ある以下のような食品は、海外で高い評価を得られるでしょう。
- 抹茶や発酵食品(味噌、醤油、漬物など)
- 海藻類
- だし(鰹節、昆布など)
なかでも発酵食品やだしなどは、健康志向の高まりや日本食ブームを背景に、世界中で人気が高まっています。
特徴5:日本らしいパッケージ
海外の消費者は、日本の食品の品質だけでなく、パッケージデザインにも魅力を感じることが多くあります。「日本らしい」と感じさせるパッケージは、商品の差別化につながり、購買意欲を高める重要な要素です。
たとえば、富士山や桜、和柄などをモチーフにしたデザインは、海外の消費者に強くアピールします。視覚的な魅力を最大限に引き出すパッケージデザインは、越境ECにおける商品の競争力を大きく高める要因となるでしょう。
特徴6:海外観光客に人気の食品
インバウンド需要の高まりとともに、日本を訪れた海外観光客が購入し、自国へ持ち帰るほど人気を得ている食品は、越境ECにおいても高い人気を得やすい傾向があります。海外観光客に人気な商品は、すでに海外での認知度が高いケースもあり、新規顧客の獲得コストを抑えられます。
具体的には、地域限定のお菓子、特定のアニメやキャラクターとコラボした食品、インスタント食品(ラーメン、味噌汁など)などがあります。訪日経験のある消費者からのリピート購入も期待でき、海外でのブランド確立につながりやすい特徴を持っています。
食品越境ECの始め方
一般的な越境ECの始め方としては、海外のモール出店や越境ECサイトの構築などが挙げられます。しかし、国内向けECサイトの越境EC対応から始め、次に海外モール出店、そして最終的に自社で越境ECサイトを構築する方法がおすすめです。
食品越境ECの始め方を詳しく見ていきましょう。
STEP1:国内向けECサイトを越境EC対応する
食品越境ECを手軽に始められる方法としておすすめなのは、現在運営している国内向けECサイトを越境EC対応させることです。越境EC向けの代理購入サービスの導入により、既存サイトを大きく改修することなく、海外からの注文を受け付けられるようになります。
たとえば、代理購入サービスを利用すれば、既存のECサイトに簡単なタグを設置するだけで、海外からの注文受付や決済処理、国際配送の手配までを外部に委託可能です。海外取引に関する専門知識がなくても、低コストかつ低リスクで越境EC市場へ参入できます。
STEP2:海外のモールに出店する
国内向けECサイトでの越境EC対応が順調に進んだら、次のステップとして海外のECモールへの出店を検討しましょう。出店先のECモールは、AmazonやeBay、Tmallなどが候補として挙げられます。
海外ECモールは、すでに膨大な数のユーザーを抱えているため、自社ECサイトだけではリーチしにくい広範な海外顧客層に、効率的にアプローチできる点がメリットです。一方で、出店には初期費用や月額手数料、売上に応じた販売手数料などがかかります。
また、モールごとに異なる規約や決済システム、配送方法などに対応する必要があり、運用コストが高くなりやすい点には注意が必要です。集客力とコストのバランスを考慮し、自社の商品やターゲット層に合ったモールを選びましょう。
STEP3:越境ECサイトを構築する
食品越境ECの最終段階として、自社独自の越境ECサイトを本格的に構築することが挙げられます。ECプラットフォームを利用すれば、簡単に多言語・多通貨対応のサイトを立ち上げられます。自社サイトは、ブランドの世界観を自由に表現できる点や、顧客データのすべてを自社で管理・分析できる点などがメリットです。
ただし、自社サイトはモールと異なり、最初から集客力があるわけではありません。集客面を含めた運用コストもかかるため、国内ECサイトと同様に、現地での認知度を高めるための広告戦略やSEO対策などをしっかりと実施する必要があります。
なお、STEP1やSTEP2を経ている場合、これまでに得られた海外市場のニーズや顧客の購買データ、売れ筋商品などの情報を活用し、より適切な戦略立案や運営方針を立てやすくなります。
食品越境ECを始める際に知っておきたいこと
食品の越境ECは事業拡大のチャンスを秘めていますが、通常のECとは異なり、食品ならではの複雑な規制や手続きが存在します。規制や注意点を知らずに販売を開始してしまうと、商品の差し止めや回収、法的トラブルに発展するリスクもあるため、注意が必要です。
ここでは、食品の越境ECを始めるうえで、知っておきたいことを4つ紹介します。
国ごとに食品輸入規制がある
食品を海外に輸出する際には、国ごとに異なる食品輸入規制や検疫条件が設けられています。国によって、以下のような規制が異なります。
- 成分表示
- 添加物の種類や使用量
- 遺伝子組み換え食品に関する規制
- 特定の植物由来成分や動物性加工品に対する検疫要件
ターゲットとする国が決まったら、まずは国の農業省や保健省、関連機関サイトなどで、輸出する食品に関する最新の規制情報を徹底的に調査しましょう。確認を怠ると、商品が税関で差し止められたり、輸入許可が下りなかったりするリスクがあるため、細心の注意を払ってください。
食品表示は多言語対応する
越境ECで販売する食品のパッケージ表示は、多言語に対応しましょう。多くの国では、現地の法律で定められた表示事項を、該当国の公用語で表示することが義務付けられています。
さらに、国によって単位の表記方法(グラム、ポンド)や、表示の様式が異なるため、現地の規制に合わせた正確な表示が必要です。輸入者が定められた形式でラベルを貼り直す義務がある場合もあるため、現地の輸入パートナーと事前に連携しておくことが重要です。表示が正しくないと、通関で問題が生じるだけでなく、現地の消費者からの信頼を失い、最悪の場合、販売停止命令や訴訟リスクにつながる可能性もあります。
国際認証を取得しておく
食品の越境ECにおいて、第三者機関による国際認証を取得しておくことは、現地の消費者や取引先からの信用力向上につながります。食品の安全性や品質に対する意識が高い国々では、国際認証の有無が購入の決め手となることも少なくありません。
代表的な認証には、以下が挙げられます。
- ISO 22000
- HACCP
- ハラール認証
- コーシャ認証
認証の取得により、製品の品質と安全性が国際的に認められていることを証明できるだけでなく、競合他社との差別化にもつながり、スムーズな海外展開を目指せます。
アレルギー表示を徹底する
食品の越境ECでは、アレルギー表示の正確性を徹底しましょう。国によっては、日本で表示が義務付けられているアレルゲンとは異なる品目が、特定アレルゲンとして指定されている場合があります。
また、表示方法も現地の消費者が容易に理解できるよう、明確かつ適切な形式で記載する必要があります。アレルギー表示の不備は、消費者の健康被害に直結する可能性があり、大規模なリコールや訴訟リスクにつながる可能性もあります。
そのため、ターゲットとする国の最新のアレルギー表示規制を徹底的に調査し、現地の法律に完全に準拠した表示をすることが、越境EC運営には不可欠です。
越境ECを始めるならfutureshopにご相談ください
食品越境ECを始めたいと考えている方は、futureshopにご相談ください。futureshopは、国内向けのECサイトだけでなく、越境ECのサポートも行っています。越境EC向けのサービスとして、代理購入サービスである「WorldShopping BIZ」や、多言語翻訳ができる「shutto翻訳」と連携しています。
WorldShopping BIZとshutto翻訳は、JavaScriptのタグを1行実装するだけで、既存のECサイトを越境EC仕様にすることが可能です。複雑な手続きをしたり、翻訳家を雇ったりする必要がないため、手軽に食品越境ECを始めたい方におすすめです。
futureshopの越境ECサービスが気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
日本の食品は、海外から高い評価を得ているため、越境ECを始めることで事業拡大を期待できます。実店舗よりもコストやリスクが低い点もメリットです。越境ECで食品を販売する際は、常温で配送できたり、賞味期限の長い商品を選んだりするのがおすすめです。
また、国によって食品輸入の規制や食品表示の決まりが異なります。規制を知らずに販売すると、関税で止められたり、最悪の場合は法的トラブルに発展したりするリスクがあるため、事前調査を徹底したうえで、食品越境ECを始めましょう。